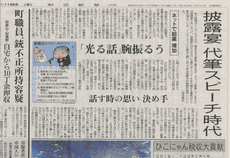結婚式の招待状が届いたのは、まだ春の寒さが残るある日のことだった。
差出人は、営業部の元部下・佐野優斗。四年目で転職していった彼が、久しぶりに連絡を寄越してきた。そして、その中に一枚の付箋があった。
「もしご都合が合えば、ぜひご挨拶のスピーチをお願いできればと思っています。
○○さんの言葉で、門出を見送っていただけたら、とても嬉しいです」
手にした瞬間、思わず口元が緩んだ。だが、すぐに背筋がピンと伸びた。嬉しさと同時に、プレッシャーが肩にのしかかってくる。
スピーチ。
それも、あいつの人生の門出の場で。
「……さて、どうするか」

私は、言葉を紡ぐ仕事ではない。営業職として二十年近くを過ごし、数字と根回しと会議に明け暮れる日々。パワーポイントなら作れるが、「心を動かす言葉」など書いたことがない。
しかし、不思議なことに、思いは溢れていた。
初めて会った日のこと。ミスをして落ち込んでいた時にこっそり机の上に置かれたメモ書き。後輩たちに見せた不器用な優しさ。あるいは、転職を切り出してきた、あの冬の夜。
あいつが去った時、私は、うまく言葉をかけられなかった。
「そうか。頑張れよ」
それしか言えなかった。ほんとは、もっと話したかった。止めたかったのかもしれない。でも、上司という立場が、言葉を奪った。
そんな後悔が、今もずっと喉の奥に引っかかっている。

ある日、同僚に何気なくこぼした。
「結婚式のスピーチ、頼まれたんだけどな……どうにも言葉がまとまらない」
すると、彼女がポンとスマホを見せてきた。
「ここ、いいらしいですよ。プロのスピーチライターがヒアリングしてくれるって」
そこに載っていた名前――「スピ子」。
冗談か?と思ったが、口コミはやけに真面目で、依頼者の感謝の言葉が続いていた。
“代筆”というより、“通訳”のように見えた。
心にある思いを、うまく日本語にできないとき。プロに頼るのは、恥ではないのかもしれない。

翌週、都内の古いビルの一室。スピ子と名乗る女性は、静かに私の言葉を待っていた。
「どうして、今回スピーチをしようと思われたんですか?」
私は少し躊躇ってから、ポツポツと語り始めた。
佐野との出会い。若手としては珍しく泥臭く、時に暑苦しいくらい仕事に食らいついてきた姿。だが、どこか一本、心に芯を通した若者だった。
「ただ、言葉にするのが難しいんですよ。仕事での関係だったし……」
「でも、お話の中には、たくさんの“情”が滲んでいますよ」
そう言って彼女は、微笑んだ。
「“仕事上の言葉”と“心の声”は、必ずしも別じゃありません。むしろ、重なったときに初めて、スピーチとしての力を持つんです」

ヒアリングは三回に渡った。
「君の成長が誇らしかった。時に、腹も立った。けれど、いつもどこか、羨ましかった」
そんな、自分でも意外な言葉が口を突いて出た。
「羨ましかった?」
「自分の信じた道を、あんなふうに潔く選べる人間って、そういない。私にはできなかったから」
それを言葉にしたとき、自分の心の奥に残っていた“欠片”のようなものが、音を立てて崩れた気がした。
スピ子は、ただ頷いていた。

提出された原稿には、こう書かれていた。
「佐野くん。君が去ったあの日、私は何も言えなかった。
本当は、止めたかったのかもしれないし、応援したかったのかもしれない。
でも、上司という肩書きが、言葉を狭めた。
だから今日、肩書きを下ろして、一人の人間として言うよ。
“君のこれからの人生が、今まで以上に美しくあるように”――
そう、心から願っている」
それは、不思議なほど私の声に近かった。けれど、自分では絶対に書けなかった。

式当日、壇上で私はスピーチを読んだ。
読みながら、自分の声が、少しずつ“人間の声”に戻っていくのがわかった。
「ありがとう、佐野」
その一言に、彼がどんな顔をしたか。よく覚えていない。
ただ、スピーチが終わったあと、彼が近づいてきて、握手の手を差し出してきた。
「……あの言葉、俺、一生忘れません」
そう言って笑った目が、どこかあの頃よりもずっと大人びていた。

スピーチは、自己満足ではない。
**「言えなかった言葉」を、今、伝えるための“勇気の器”**なんだと、私は思う。
そしてそれを、誰かが“言葉にしてくれる”ということは、恥ではなく、誠実さのかたちなのかもしれない。

スピ子から、後日短いメッセージが届いた。
「あの日の“沈黙”が、言葉に変わる瞬間に立ち会えて、私も嬉しかったです。
言葉は、いつでも、遅れて届いてもいいんです。
そのほうが、まっすぐ届くこともありますから。」
私は、スマホを閉じてひとつ深く息を吸った。
これから、また部下が成長し、去っていくだろう。きっとそのたびに、私はまた言葉を探す。
でも、もう大丈夫だ。
心にしまった“本当の声”を、今度は自分の言葉で、少しずつ伝えられる気がしている。